心理的ウェルビーイングと日記の効果
「またあの人に振り回された…」
職場でそんなふうに感じたこと、
ありませんか?
上司の一言に落ち込む。
同僚と比べて焦る。
30代になると責任も増え、
人間関係のストレスは
どんどん大きくなります。
残念ながら、嫌な人を
消すことはできません。
でも――あなたの 心の土台 を
強くすることはできます。
心理学ではこれを
心理的ウェルビーイング(PWB) と呼びます。
「気分がいい」だけではなく、
自分を受け入れ、
人と良い関係を築き、
環境に適応しながら
成長していける心の状態のこと。
そして、このPWBを育てる
シンプルな方法が 日記習慣 です。
感謝日記・よかったこと日記・
自分ほめ日記。
ほんの数行の記録が、
ストレスに強い心を
少しずつ育てます。
嫌な人はなくならなくても、
あなたは鬱に負けない自分をつくれる。
この記事では、その具体的な方法を
お伝えします。
なぜ職場のストレスはなくならないのか

「もう少し環境が良ければ…」
「嫌な人さえいなければ…」
そう思ったことはありませんか?
実際のところ、職場のストレスの多くは
自分ではコントロールできない外部要因
によって生まれます。
- 上司の性格や指導スタイル
- 同僚や後輩との相性や評価
- 組織の雰囲気や社風
これらを根本的に変えることは
私たち個人にはほとんど不可能です。
「嫌な人をなくす」ことは
できないのです。
だからこそ大切なのは、
ストレスにどう向き合うか。
同じ出来事でも
「気にしすぎて落ち込む人」と
「切り替えて前に進める人」がいます。
この違いを生むのが、
心理学でいう 心理的ウェルビーイング(PWB) です。
PWBは、
- 自分をどう受け止めるか
- 人との関係をどう築くか
- 環境にどう適応するか
といった「心の土台」を整える考え方。
PWBを高めることで、同じ職場にいても
ストレスをため込みにくい心 を
育てられるのです。
PWB(心理的ウェルビーイング)とは?

ストレスをため込まない心をつくるために
重要なのが、心理学者キャロル・D・ライフ
(Ryff, 1989)が提唱した
「心理的ウェルビーイング(PWB)」 です。
「ウェルビーイング」という言葉を聞くと、
「楽しい気分」や「ポジティブ思考」を
想像するかもしれません。
でも、PWBは一時的な気分ではなく、
心の健康や生き方そのものの質 を
示す概念です。
ライフは、人が心理的に健やかに
生きるためには6つの要素が必要だとしました。
- 自己受容(Self-acceptance)
- ポジティブな対人関係
- 自律性(Autonomy)
- 環境制御力(Environmental mastery)
- 人生の目的(Purpose in life)
- 自己成長(Personal growth)
この6要素がバランスよく育っていると、
ストレスや逆境に強くなり、
鬱などのメンタル不調を
防ぎやすくなるとされています。
実際、RyffとKeyes(2002)の研究では、
PWBの高さが「抑うつ症状の少なさ」や
「幸福感の持続」と関連していることが
示されています。
今回紹介する 日記習慣 は、
この6つのうち特に
- 自己受容
- ポジティブな対人関係
- 自律性
- 環境制御力
- 自己成長
を自然に育てるのに効果的です。
つまり、毎日の小さな記録が
「心のウェルビーイング」を整え、
ストレスに強い自分をつくる
土台になるのです。
よかったこと日記 × 環境制御力・自己成長

「今日はこれがよかった」と
一日の終わりに振り返る。
ほんの数行でも
「よかったこと日記」をつけると、
気分が少し軽くなる経験は
ありませんか?
この習慣は 環境制御力 と
自己成長 を高める働きを
持っています。
環境制御力を育てる
「よかったこと」を探す過程で、
私たちは無意識に
「環境の中で自分ができたこと」に
目を向けます。
たとえば――
- 忙しい中でも書類を仕上げられた
- 会議で意見を言えた
- 天気がよくて通勤が気持ちよかった
こうした出来事を拾い出すことで、
「自分には環境を
ポジティブに変える力がある」と
実感できます。
それは無力感をやわらげ、
ストレスに押しつぶされにくくする
土台になります。
自己成長を実感する
「昨日より今日できたこと」を
記録すれば、成長を実感できます。
- 「先週より落ち着いて対応できた」
- 「苦手な人に笑顔で挨拶できた」
些細なことでも、
積み重ねて書くことで
「自分はちゃんと前に進んでいる」と
思えるようになります。
この感覚が、ストレスを
「ただの負担」ではなく
「成長の糧」として受け止める力に
つながります。
自分ほめ日記 × 自己受容・自律性

「今日はあの資料を丁寧に仕上げられた」
「苦手な電話対応を最後までやり切った」
そんなふうに、一日の中で
自分ができたことを一つ
書き出してみる。
これが 自分ほめ日記 です。
一見シンプルですが、
心理学的に見ると 自己受容 と
自律性 を強める働きがあります。
自己受容を高める
人はつい「できなかったこと」や
「他人と比べて劣っていること」に
意識を向けがちです。
その結果、「自分はだめだ」と
自己否定に陥り、
ストレスを増幅させてしまいます。
自分ほめ日記は、その逆を促します。
- うまくできた小さなこと
- いつもより頑張れたこと
- 誰にも気づかれなかった努力
こうした「自分だけの成果」を書くことで
「私はこれでいい」と思えるようになり、
自己受容の感覚が少しずつ育っていきます。
これは鬱の予防にとても有効です。
自律性を育てる
他人の評価に振り回されず、
自分で自分を認められること。
これが自律性です。
職場ではどうしても、
上司や同僚の評価に一喜一憂しがち。
でも「今日の自分を自分で褒める」
習慣があれば、他人の目に
左右されにくくなります。
- 「上司には認められなかったけど、
自分なりに精一杯やった」 - 「結果は出なかったけど、
挑戦した自分は偉い」
こうした視点が身につくと、
ストレスのダメージを
大きく減らすことができます。
感謝日記 × ポジティブな対人関係

「同僚が手伝ってくれた」
「家族が温かい言葉をかけてくれた」
「コンビニの店員さんが笑顔で対応してくれた」
日常の中で感じた小さな「ありがとう」を
書き留めるのが 感謝日記 です。
この習慣は、心理学でいう
ポジティブな対人関係 を
育てる大きな効果があります。
人間関係のプラス面に気づく
職場の人間関係は、
ストレスの最大の原因になりがち。
しかし感謝日記を続けると、
「嫌なこと」ばかりに意識が向かず、
「支えてくれること」「助けてもらっていること」
にも気づけるようになります。
これは「自分は一人じゃない」という
安心感につながり、
孤独感をやわらげます。
感謝はストレスのクッションになる
心理学研究でも、
感謝の習慣がストレスを軽減し、
鬱や不安を防ぐことが示されています。
人に対して感謝を抱くと、
オキシトシン(安心感をもたらすホルモン)が
分泌されるともいわれています。
つまり「ありがとう」を意識するだけで、
心身が回復しやすくなるのです。
関係性が好循環を生む
感謝日記を習慣にしていると、
自然に人に優しく接することが増えます。
その結果、相手からも
ポジティブな反応を受けやすくなり、
人間関係全体が好循環に。
「嫌な人がゼロになるわけではない」
けれど、「味方はちゃんといる」と
実感できるのです。
日記で“鬱にならない心”を育てる

職場の嫌な人や理不尽な状況を、
自分の力で消すことはできません。
しかし、自分の心の土台を
整えることは誰にでもできます。
心理学者ライフのPWB理論に照らすと、
- よかったこと日記 は
「環境制御力・成長」を育てる - 自分ほめ日記 は
「自己受容・自律性」を支える - 感謝日記 は
「対人関係の安心感」を強める
毎日数行書くだけで、
- 自分を否定しすぎない
- 成長を実感できる
- 人とのつながりに気づける
そんな “鬱にならない心” が
育っていきます。
大きなことを書く必要はありません。
一行でも、ひとつでもいいのです。
小さな積み重ねが、
ストレスに負けない強さをつくるのです。
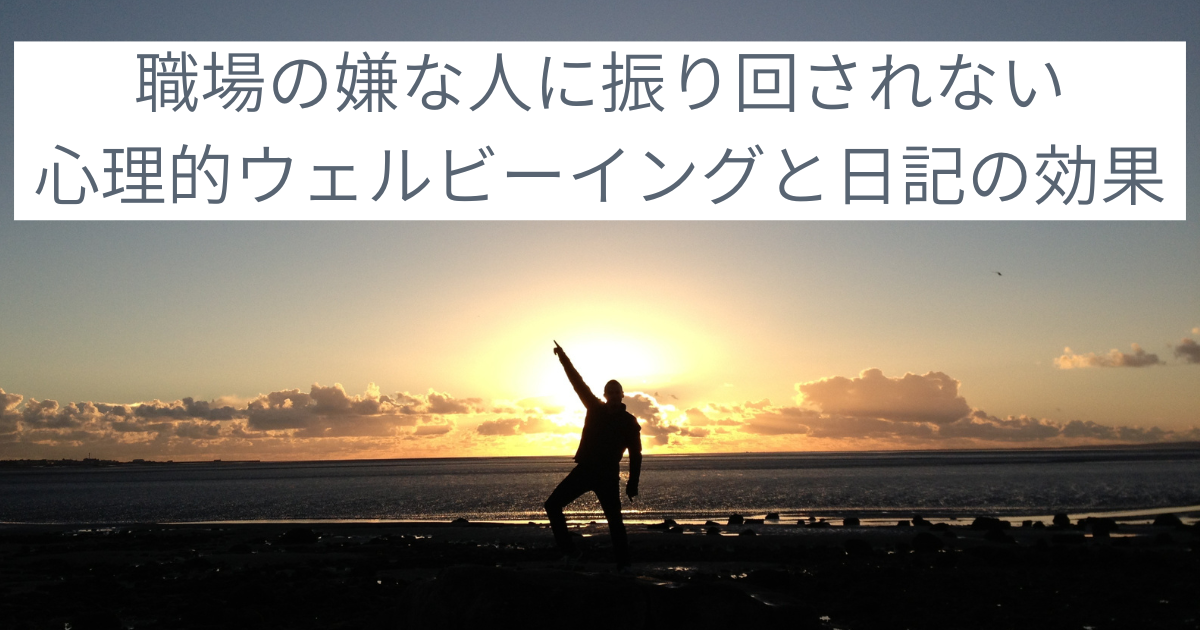
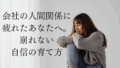
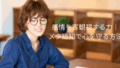
コメント